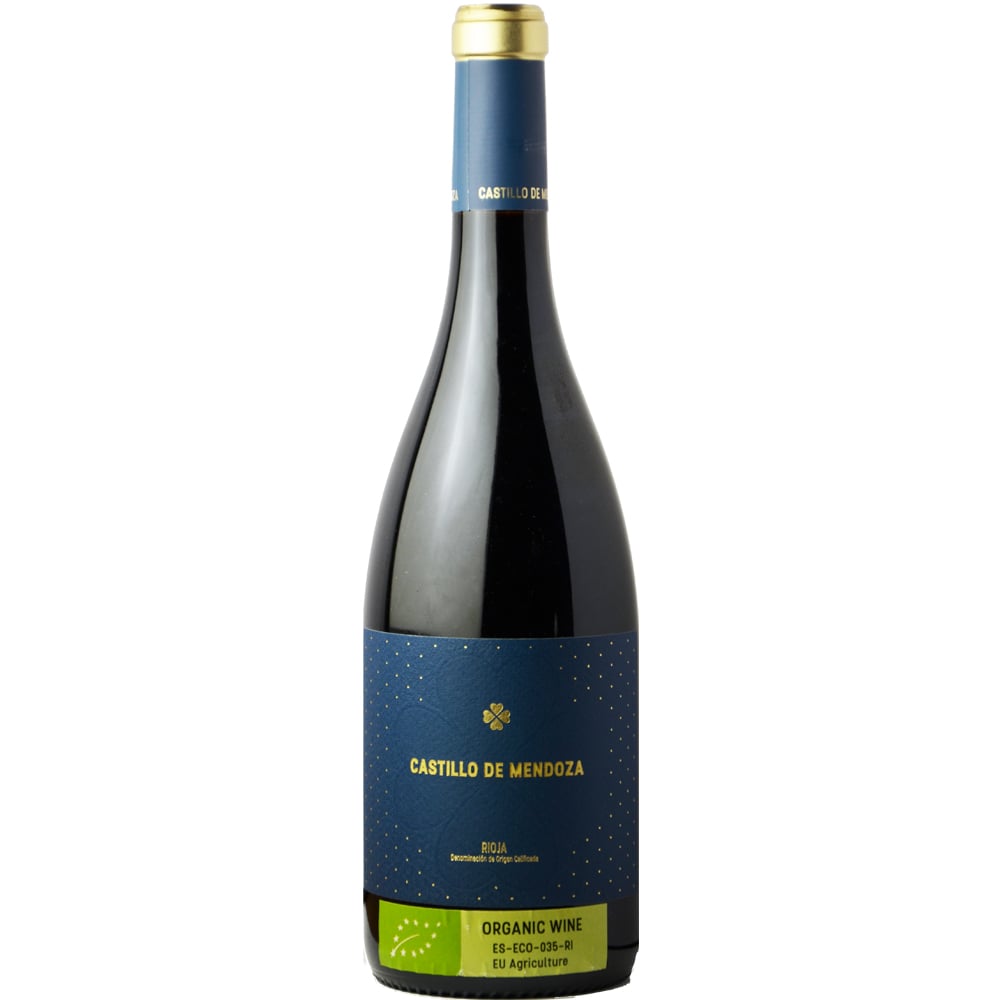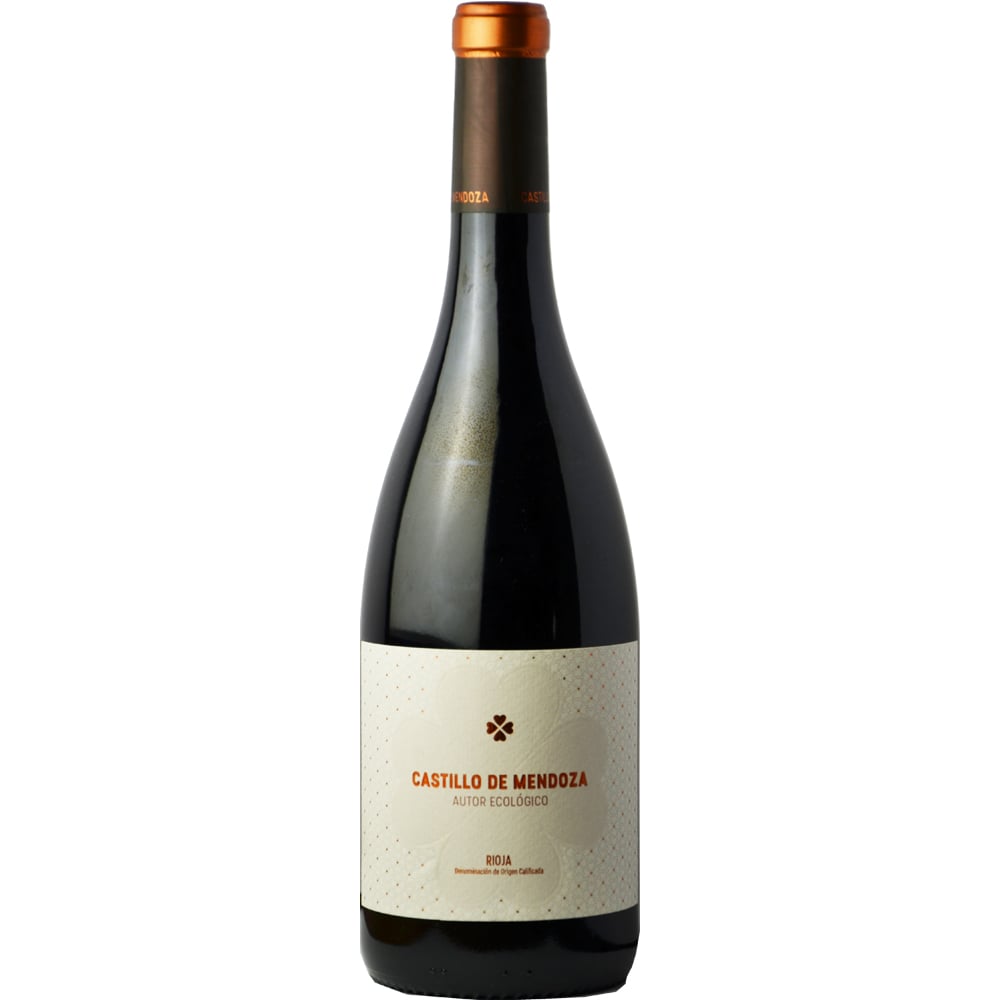45年前のリオハ初訪問はワイナリー原体験
1980年7月7日、ヘミングウェイの「日はまた昇る」に感化された僕は、どうしてもサン・フェルミン祭の牛追いを見たくてスペイン北部パンプローナに居た。
サラマンカからヒッチハイクで前日到着、闘牛場前の路上の一番いいポイントで場所取りのため大勢の若者たちと騒ぎながら夜を明かしたのだが、牛追いの始まる直前に警官隊がやって来たと思ったら、立ち入り禁止となって、全員排除されてしまい、結局群衆にもみくちゃにされながら、何も見えず6頭の牛たちと追われて走る人々の声と足音を聞いた。
牛追いが終わると若者たちは一緒に昼食を取って、ひとしきり飲み解散、それぞれヒッチハイクで帰路につき、僕は隣の県に向かうルノー5のドライバーに拾ってもらった。このドライバーはV.F伯爵という貴族で、城に泊れと誘ってくれた。リアルシャトーに泊まれるとワクワクしたのは22歳の本心だ。
彼の城の近くだというHaro(アロ)という町で一杯飲もうと言われ、Barに入ってワインを飲んでいたところ、ある家族が割り込んできた。その家族の父親は伯爵に対して、僕を車から降ろして置いて行くようにと喧嘩口調で言った。実はこの伯爵は地元では若い男性を漁ることで評判の人物で、そのBarの客たちも皆賛同したので、伯爵は仕方なく僕を開放することになり、悪態をつきながら一人で出ていった。そしてこの家族が僕を泊めてくれることになったのだが、これが幸いした。
ワインが大好きだと言ったら、友人がワインメーカーやっているからと、その場で電話してくれて、翌日7月8日、Viña Tondoña(ビニャ・トンドーニャ)に連れて行ってくれた。高品質なワインしか造らない銘醸蔵だ。それが僕にとって初めてのワイン生産者訪問。
当時、スペインではリオハは今以上に特別な存在だった。レストランでもバルでも酒販店でもワインは、普通のワインか、リオハの二択だが、リオハにはブランドのチョイスができ、そのブランドの中でもViña Tondoñaは別格だった。
ちょうどアルゼンチンのインポーター夫妻の訪問と重なって、社長自ら案内してくれたが、何と言っても初めての体験で、「ここの井戸はワイン醸造に適しているのか?」という質問をしたところ、一瞬キョトンとされ、「ワインの水分はブドウが畑の地下水を汲み上げたもの。」と笑いながら答えてくれたのが忘れられない。
こうして、ワインは乾いた米から造る日本酒と根本的に違うことを知ることができた。また狭いリオハ地方だけでは原料ぶどうが足りないため、ラマンチャやエストレマドゥーラで原料ワインを桶買いしていることと、醸造時の糖分添加(シャプタリゼ)を行っていることなど、裏話を隠すことなく聞かせてくれたのは、僕にとって強烈な原体験となった。
高級リオハ ワインの中心地Haro

性格が大きく異なるリオハの3地域
リオハのブドウはリオハ・アルタ、リオハ・アラベサ、リオハ・オリエンタルの3つの地域で栽培されているが、標高や気温、湿度、カンタブリア山脈やエブロ川の影響などで性格はまるで違う。ちなみにリオハ南部は険しい山岳地帯でぶどう栽培はできない。
| 地区 |
標高 |
気候条件 |
特徴 |
主な品種 |
| Rioja Alta |
400〜600m |
大西洋の影響を受け冷涼、降水量も多め |
長期熟成向きの骨格ある赤ワイン。酸がしっかり残る |
テンプラニーリョ主体、マスエロ、ガルナッチャ少量、白はビウラ |
| Rioja Alavesa |
400〜700m |
大西洋性が強く、昼夜の寒暖差大 |
果実味と酸のバランス良好、上品で香り高い赤ワイン |
テンプラニーリョ比率が非常に高い(7〜8割)、若飲み・熟成両方可能 |
| Rioja Oriental(旧Baja) |
200〜400m |
地中海性で乾燥・高温、降雨少 |
力強くアルコール高め |
ガルナッチャ主体、テンプラニーリョ、グラシアーノ。白はマルヴァシアも |
僕が覚えた時代は「リオハ・オリエンタル」ではなく「リオハ・バッハ」(Rioja baja)と呼ばれていたが、baja(低い)ではイメージ的にも格下に聞こえるということで、2018年に東部を意味するオリエンタルに改称されたそうだ。
こんなに性格が違うのに、なぜDOC リオハという一つの呼称しかないのか不思議だが、実は生産者間では長年の対立があり、リオハ・アルタとリオハ・アレアラベサの小規模生産者達は、ブルゴーニュのようなそれぞれの地区DOCや、さらに村名DOCを獲得したいと願ってきた。
アロ市に本拠地を置く大手・準大手ワインメーカー
リオハ県北西端のアロ市はリオハワインの中心地で、トンドーニャを始め数多くの有名蔵が集まる。大手・準大手だけで8社もあり、8社の合計生産量は5000万本に上る。そのほぼ全てがボトルで販売される高級ワインばかりだ。
ただこれらの大メーカーの自社畑が広い訳ではなく、原料ブドウの大部分を購入しており、遠方のリオハ・オリエンタル地区で収穫されたものだ。
| クラス |
ワイナリー |
推定生産量(本/年) |
| 大手 |
CVNE(Cune, Imperial, Viña Real等) |
約2,000万本 |
| 大手 |
La Rioja Alta, S.A. |
約700〜800万本 |
| 大手 |
Bodegas Bilbaínas(Viña Pomal) |
約600〜700万本 |
| 準大手 |
Muga |
約500〜600万本 |
| 準大手 |
López de Heredia Viña Tondonia |
約300〜400万本 |
| 準大手 |
Gómez Cruzado |
約100万本 |
| 準大手 |
Roda |
約200万本 |
| 準大手 |
Martínez Lacuesta |
約200〜300万本 |
大手メーカーが牛耳るリオハ
| 区分 |
社数 |
推定生産量ボトル (L) |
% |
推定生産量バルク (L) |
合計 (L) |
| 大手 |
12 |
120,000,000 |
60 |
0 |
120,000,000 |
| 準大手 |
9 |
20,000,000 |
10 |
0 |
20,000,000 |
| 協同組合 |
37 |
8,000,000 |
4 |
22,000,000 |
30,000,000 |
| 小規模 |
211 |
52,000,000 |
26 |
18,000,000 |
70,000,000 |
| 合計 |
269 |
200,000,000 |
100 |
40,000,000 |
240,000,000 |
ボトルワイン生産に限ると、大手12社は60%を寡占している。これに準大手9社を合わせると70%に達することになり、当然発言権が強い。大手や準大手メーカーは自社畑をほとんど持っておらず、3地区のブドウ農家から原料を仕入れて仕込んでいる。これはシャンパーニュのエペルネとランスに集まる大メーカー達(ネゴシアン マニュプラン)を彷彿とさせる。
シャンパーニュと同じブランドマーケティングの構図
ブランドマーケティングの場合、ワインは常に均質でなければならない。そして均質なワインを大量生産するためには、地区の異なるブドウを使ってブレンドする。こうして大手や準大手メーカーはスペイン中のデパート、スーパーマーケット、飲食店に並べ、さらにアメリカやイギリス等海外に輸出、ブランドマーケティングを展開している。これはまさにシャンパーニュと同じだ!
ここで地区ごとに異なるDOCが導入されたら、ブランドマーケティングの成果である「DOCリオハ」の価値が下がることになるので、大メーカーは地区DOCや村名DOCを認めたくない。
またリオハ・アルタの小規模生産者達は、DOCリオハにぶら下がっている方が得だと考え、やはり反対に回るから、多勢に無勢なのだろう。
興味深いリオハ・アルタとリオハ・アレアラベッサの小規模生産者
とはいえ近年は、より上級・上質を求める動きに歯止めをかけることができなくなり、リオハ・アルタとリオハ・アレアラベサの小規模生産者が脚光を集めるようになってきた。
リオハ各地区の小規模生産者数
| 地区 |
小規模生産者数 |
% |
| Rioja Alta |
80軒 |
38% |
| Rioja Alavesa |
85軒 |
40% |
| Rioja Oriental(旧Baja) |
46軒 |
22% |
| リオハ全体 |
211軒 |
100% |
リオハ・アルタ地区とリオハ・アラベサ地区には、リオハ全体の8割近い小規模生産者が集中しており、面積の広いリオハ・オリエンタル地区には醸造まで行う生産者が少ない。
リオハの銘醸地はどこ?
「小規模=テロワール表現や単一畑ワイン」とすれば、必然的に高品質でなければならず、それが狭いエリアに集中している。そして本当の銘醸地は東西わずか30㎞にある8村でしかない。
| 地区 |
村名 |
小規模独立生産者数 |
| Rioja Alta |
Haro |
40〜50軒 |
| Rioja Alta |
San Vicente de la Sonsierra |
約30軒 |
| Rioja Alta |
Briones |
15〜20軒 |
| Rioja Alta |
Cenicero |
約20軒 |
| Rioja Alavesa |
Laguardia |
50〜60軒 |
| Rioja Alavesa |
Elciego |
約20軒 |
| Rioja Alavesa |
Labastida |
20〜25軒 |
| Rioja Alavesa |
Villabuena |
40〜50軒 |
この数字を見ると生産者数が多過ぎると感じるかもしれない。これは1軒の生産者が複数の村に畑を持っているため、重複してカウントされているためだ。
リオハはブルゴーニュのような細かい区画の畑
リオハ地方の相続制度が長子相続ではなく、均等相続だったため、畑は代々分散して単位が小さくなり、それが相続や売買で複雑化したのだ。ブルゴーニュと同じ図式で、醸造家の腕が鳴るところだ。畑の規模はミクロという程の小ささで、意欲的な小規模生産者が購入しやすく、あちらこちらとモザイク化していく。固定化してしまったブルゴーニュよりも面白い。
その8村の中で、今最も注目されているのが サン ビセンテ デ ラ ソンシエラ (San Vicente de la Sonsierra)と Briones (ブリオネス)だ。この2つの村はアロ市の南東5~6kmで、エブロ川を挟んで隣り合っている。
どちらも高地ではあるが、サン ビセンテ デ ラ ソンシエラは北のカンタブリア山脈に連なり、まさにコート ドールのように複雑な地層が入り組んでいる。高度が高く冷涼な気候はブドウにキレのいい酸をもたらす。ブドウ栽培の条件は最高レベルと言える。
そのサン ビセンテ デ ラ ソンシエラのCastillo de Mendoza(カスティーリョ デ メンドーサ)が、マヴィの生産者に加わることになり、4月に訪問してきた。
サン ビセンテ デ ラ ソンシエラ

カンタブリア山脈とサン ビセンテ デ ラ ソンシエラの村
ログローニョからの国道バイパスをブリオネスで降り、北のカンタブリア山脈へ向かって走ると、すぐに断崖に立つ サン ビセンテ デ ラ ソンシエラ村が見えてくる。中央に中世の城塞がそびえ、息を吞むほどに美しい景色だ。
蛇行するエブロ川に架かる橋を渡り、急坂を登り村に入る。細く曲がりくねった道と中世の佇まいが色濃く残る街並みは、どこを取っても絵になる。慎重に村の中心を抜けて縦断、村はずれの小川を狭い道幅の橋で渡ると、右手に目的地カスティーリョ デ メンドーサが見えた。
カスティーリョ デ メンドーサ
バスク地方サン セバスチャンの実業家・エロイ アントニオ メンドーサさんにとって、サン ビセンテ デ ラ ソンシエラは少年期を過ごした先祖代々の家がある、いわば故郷ともいえる村だ。
事業で成功した彼は1994年、実家が所有していた古い小さな醸造所を再興しようと、元蒸留所だった建物を修復してカスティーリョ デ メンドーサを建設、その後2001年にこの素晴らしい醸造所を新築した。スペイン語でカスティーリョはシャトー、メンドーサ家の城という訳だ。
規模は決して大きい訳ではないが、すばらしく考え抜かれたデザインは美しい。

中に入るとレセプションとテースティングルーム。畑から掘り出された石が詰まった鉄籠が、パーティッションやグラストップテーブルの台に使われて、実に秀逸。居心地がいい。ちょうど犬を連れたイギリス人夫婦がワインを買いに立ち寄っていた。
醸造タンクはどれも小振りで大小様々、材質はステンレスや樫木を使い分けている。畑ごとに仕込み、特性を最大限に引き出すのだろう。スペイン的大規模感が皆無で、まるでドイツ系醸造家のような繊細さが感じられる。

とりわけ地下の貯蔵空間は、地下湧水が絶えず岩盤の岩肌に流れるため、天然エアコンの役割を果たして、1年中温度差が全くない理想的なセラーになっている。
サン ビセンテ城内に残る発祥の地
カスティーリョ デ メンドーサは、サン ビセンテデ ラ ソンシエラの城壁の中に太古からある醸造所から、村はずれの広い醸造所へ移転してきた。
 城壁の中にある発祥の地
城壁の中にある発祥の地
発祥の地はこの石造りの小屋。サン ビセンテ城の中にあり、建物は小さいが、そのまま横穴の洞窟と繋がっている。村の中は中世の道そのままで、収穫したブドウを運び込んだり、出来上がったワインを出荷してたというのがにわかに信じられないのだが、実際やっていたのだから驚く。おそらく人海戦術しかなかっただろう。
小さい区画のぶどう畑がたくさん

カスティーリョ デ メンドーサには数十カ所の細かい区画のぶどう畑があり、合計35ヘクタール。リオハ・アルタだけでなくリオハ・アラベサのバスティーダ(Bastida)にもある。と言っても隣村でわずか3㎞ほどの距離しかないのだが、州境を超えてバスク地方に入る。

リオハ地方とカスティーリャ地方を区切るデマンダ山脈の高峰、サン・ロレンソ山(2271m)を望む山中の狭い区画のぶどう畑は、断層直下で複雑なミネラル層だ。周囲の樹々でわかる通り地下水に恵まれた理想的なミクロクリマ。湿気を嫌ってか、ぶどうの蔓が高く伸ばせるようワイヤーが張られている。

粘土質の断層が露出する斜面区画のぶどう畑には樹齢50年を超すテンプラニーリョ。力強さと酸のバランスが期待できる。湿気の心配場なくワイヤーは張らず開放的。

高度400~600mで、あちこちに点在するぶどう畑、ミクロクリマが影響して土壌の種類のバラエティーが豊富で、気温、湿度、風向き、ぶどうの栽培方法もその場所に応じて変えているが、畑管理責任者のフランシスコさんはすべての区画の詳細を把握していて、常に的確な判断を完全な対応を取る。
リオハと一括りにされるのではなく、畑の区画ごとの特長を最大限に引き出すことが、個性豊かなワイン造りに繋がるのは、マヴィの生産者さん達と完全にシンクロする。
初めてテイスティングしたメンドーサ家のワイン

メンドーサ家は、マヴィの商品担当新エース・塩澤 悠が今年2月のバロセロナ ワインウィークで出会った生産者だ。彼が惚れ込み、これまでのマヴィの常道を外して、僕の試飲を経ずに取引を決めた。なので少々ドキドキでテイスティングに臨んだ。
並べたワインを軽いものから順に試飲していくのだが、まずはワインのみを確かめて吐器に捨てる。もったいないが仕方ない。どのワインも味も香りも素晴らしい。
若いワインはモダンで飲みやすい仕上がりだが、酸味とコクのバランスがよく、絶妙に美味しい。
熟成のレセルバやグランレセルバは伝統をしっかりと感じさせる、重々しい品格を持ち、すこぶる旨い。
もちろん合格だ。安心してタパスを運んでもらい、マリアージュを試すことにしたが、地元産の生ハム、チョリッソ、羊乳のチーズ等との相性を確認した。もちろんすべてパーフェクトだったのは言うまでもない。
メンドーサ家の総合評価は100点満点と言って過言ではない。来てよかった!
オーナー・エロイ アントニオ メンドーサさんからのメッセージ
ただ今回はちょうどマドリッドで大きなワイン展示会があり、オーナーのアントニオさん、総責任者のマルタさん、醸造家のマリアさんが不在で、話を聞くことができなかったのが残念だった。と思っていたらマヴィの経営本部長・羽鳥理香が5月末にスペインに行くことになり、彼女が会ってメッセージをもらって来てくれたので紹介したい。
カスティーリョ デ メンドーサのワイン

価格取得中…
マセラシオン カルボニック製法の軽やかでジューシーな赤
ヴィンテージ:2024年

価格取得中…
ステンレスタンクで醸造後、アメリカンオークで12ヶ月熟成
ヴィンテージ:2022年

価格取得中…
凝縮した果実味と骨格を愉しむ、ガストロノミック・ロゼワイン
ヴィンテージ:2024年

価格取得中…
樽発酵&樽熟成が織りなす、芳醇白ワイン
ヴィンテージ:2024年

価格取得中…
アメリカンオークとフレンチオークで18ヶ月熟成
ヴィンテージ:2021年
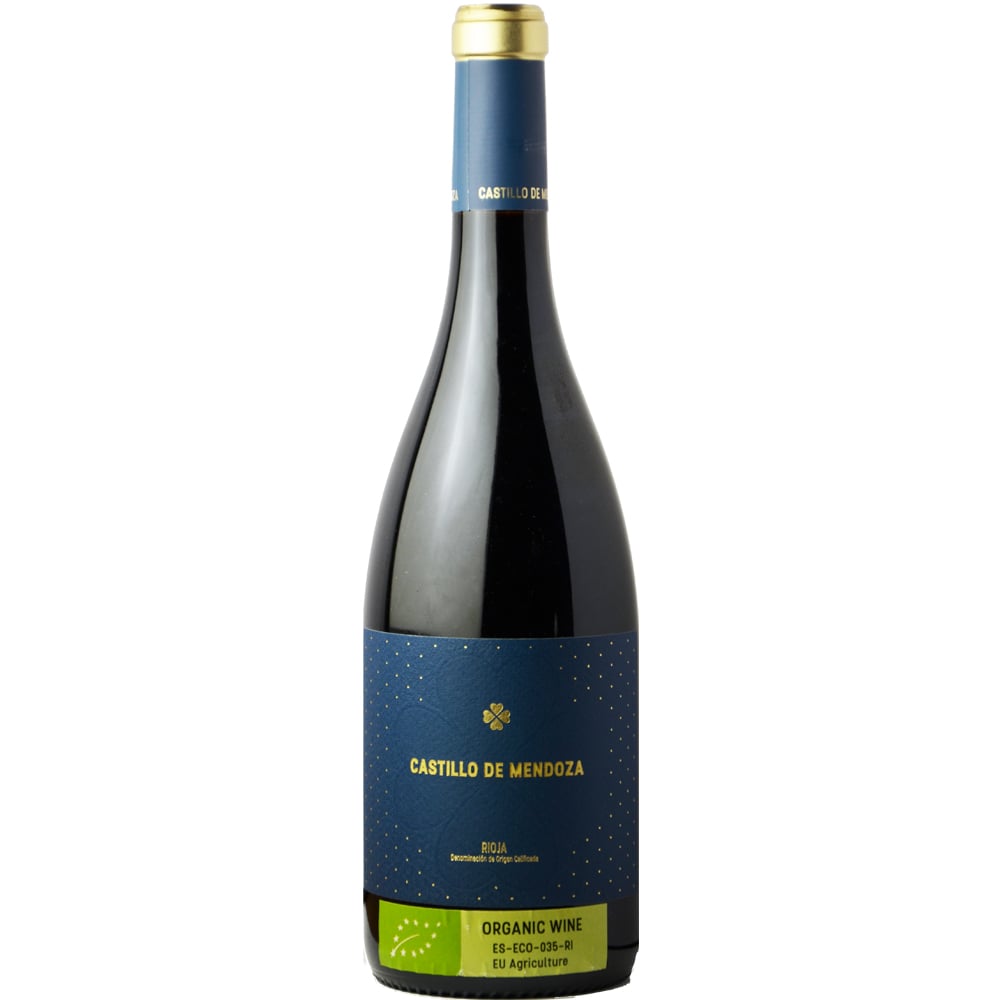
価格取得中…
フレンチオーク新樽で24ヶ月熟成後、瓶内熟成24ヶ月
ヴィンテージ:2020年
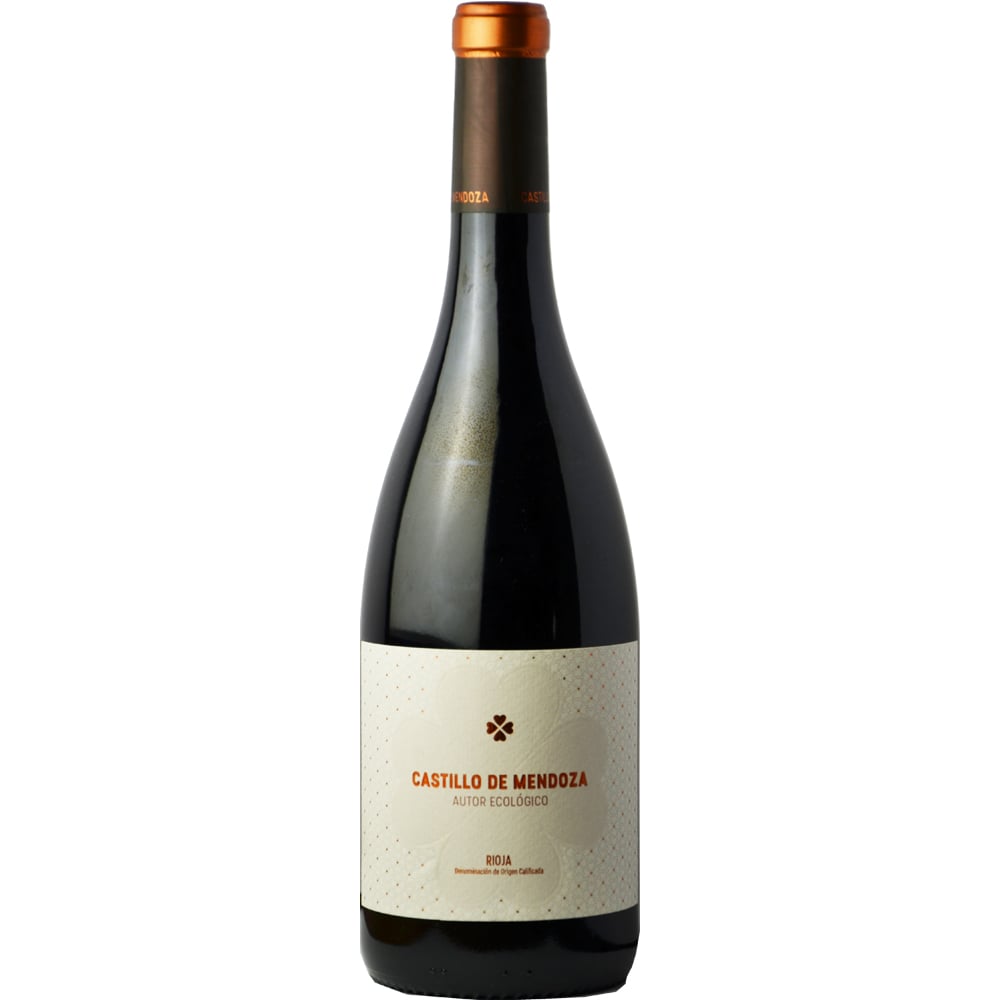
価格取得中…
500Lのフレンチオーク新樽で20ヶ月熟成
ヴィンテージ:2020年

価格取得中…
500Lのフレンチオークで醸造後、そのまま12ヶ月間熟成→255Lのフレンチオーク新樽に移し24ヶ月間熟成
ヴィンテージ2018年